うつ病は心の風邪
と言われることがあります。
たしかに
心が疲れているという表現は
全体をざっくり想像するのには
とっつきやすいと思います。
けれど
うつと長い時間つきあってきて
そのうえ適応障害も発症して
僕はこう考えます。
うつとか適応障害は
“心の問題”ではなく
“脳の機能不全”である。
もちろん
悩みやストレスなどの「心因」から
始まることもあります。
でもいったん発症すると
まるで自分の意思ではどうにもならない
「身体的・機械的な不調」が
日常を支配しはじめます。
その感覚は
「心の病気」では説明しきれない
と感じます。
今回は僕が
「うつ病=脳の病」
と捉えるようになった理由と
対処法について書いてみようと思います。
あくまで自分が調べてやってみて
いいと思えたものでしかありませんが
一つの体験談として共有します。
「心の問題」では説明しきれなかった現実
最初にうつを発症したのは今から10年前です。
よくよく思い出せば
発症した当初も危ないことはあったのですが
断続的な症状と付き合ううちに
波があるのが普通の状態になっていて
抑うつ気分の影響を忘れていました。
でも新たに発症した適応障害の前では
慣れなんてものは力を持ちませんでした。
- 夕食後に襲ってくる
どうしても身体が動かない感じ - 子どもの大声を聞いただけで
心臓がバクバクしてパニックになる感じ - いつも頭に靄がかかっている感じ
- 好きなことをしても全く楽しくない感じ
「気の持ちよう」でどうにかできるレベルじゃ
ありませんでした。
僕の場合、発症の原因は
家庭内のストレスと
仕事の悩みでした。
前の記事でも書いたように
家族に打ち明けて生活スタイルを変えても
関係者と話して仕事の悩みを整理しても
症状は改善しませんでした。
「なぜ治らないのか」と焦って
悪化する時期もありました。
毎日やってくる暗い想像をやり過ごしながら
手当たり次第に因果関係を調べるうちに
これは「心」の問題ではなく
身体が、とくに「脳」が
変調をきたしているのではないか
と思うようになりました。
「脳の病」と捉えたことで変わったこと
うつ病を
「脳の機能障害」
だと捉えるようになってから
僕は目指す方向を
「症状をなくす」から「身体を整える」に
シフトしました。
具体的には
心療内科でもらった薬を呑みながら
- 自律神経を整える
- 内分泌系をサポートする
ことをはじめました。
たとえば以下のような生活習慣の見直しです。
- 16時間断食:慢性的な炎症の抑制と腸内環境の改善を狙って実施
- 冷水シャワー:交感神経を刺激するのとドーパミンの分泌を促すために導入
- 瞑想:脳の構造変化と抗うつ剤的な効果を期待して習慣化
- 食事の見直し:ビタミンDやトリプトファンやオメガ3脂肪酸を含む食材摂取
- 自重筋トレ・HIIT:ドーパミン・セロトニン・エンドルフィンといったホルモンの分泌を促すために継続
これらの習慣は
どれもすぐに効果が出るわけではありません。
でも「身体さえ整えれば自力が生かせるはず」
という仮説の目標を設定することで
具体的にやることを決めることができ
焦りや無力感を減らすことができました。
精神論ではなく
肉体的なアプローチです。
「脳の病」という理解がもたらす希望
うつ病を「脳の病」と理解することは
僕にとって絶望ではありませんでした。
むしろ希望が生まれました。
風邪と同じようにうつも
「身体が原因ならフィジカルに対処できる」
と思えたからです。
個人差も大きい病気ですが
少なくとも僕は
「身体を整える習慣」に集中することで
自己効力感も高まって
少しずつ調子を取り戻すことができました。
「心の弱さではない」とわかること。
「治す方法がある」と信じられること。
うつは甘えや弱さという
精神的な弱点だけが原因ではありません。
ましてや
「繊細だから」
となかば揶揄されるものでもありません。
ストレスによって調子が崩れた
肉体的な症状でもあると思います。
極論、怪我と一緒だと考えます。
きちんと休めば、回復します。
自分自身で証明しながら
その過程も共有していけたらと思います。

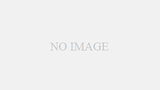
コメント