僕は気がつくと
毎日の生活はただ仕事と
家事育児をこなすだけで
精一杯になっていました。
そのうえさらに
適応障害やうつの波がくるので
毎日がギリギリでした。
このままではいけない
と頭ではわかっていても
何をどう変えればいいのか
分からない。
そんななか切実に
よくなりたい
と頭のなかで言語化したとき
現実に行動しなくてはいけない
と気づきました。
とても小さな、でも現実的な
行動のきっかけだったと思っています。
この記事では
その最初の一歩となった
3つのポイントを紹介します。
概要
よくなりたい、と思うだけでは
何も変わりません。
しかし、その雫のような考えが
内面に小さな波紋を広げ
やがて行動へとつながり
また健康だったときのように
動き続ける内面につながるのだと思います。
僕の場合、その波紋は
以下の3つの雫からはじまりました。
- 朝起きたときの行動を変える
- 小さな達成感を積み重ねる
- 使う言葉の角をなくす
これらは、派手な自己改革ではなく
ごく日常の中で意識できる
ほんの少しの工夫です。
しかし、それらを積み重ねることで
心身の負荷が徐々に軽くなり
自己肯定感が育まれていきました。
実際やってみたこと
朝起きたときの行動を変える
いちばん状態がよくないときは
アラームを止めたその流れで
SNSを見ていました。
ねむー、だるー
と考えがちなところに
よくないニュースをいきなり見るのは
今思うと最高に最低な習慣でした。
身体が起き切っていないところに
嫌な表現で頭をいっぱいにしてしまう。
いいことがあるわけありません。
なのでアラームを止めたら
スマホから手を離すようにしました。
そしてすぐに布団をたたむ。
それからすぐに口をすすぎに行く。
ここまでやると
自分の身体や意識が
自分のペースで立ち上がる邪魔をしません。
この、自然な朝のスタート
がきれるだけで
一日の気分が全然違ってきます。
一日の時間を
誰かに合わせず
自分のものとして過ごす入り口
を選ぶ感覚です。
ここ間違わなければ
大体勝つことがわかりました。
あくまで僕の場合ですが。
小さな達成感を積み重ねる
これは前の記事でも書きましたが
放送大学の勉強に打ち込むことが
達成感の源になりました。
適応障害を発症したときは
すでに学生生活も2年目に
入っていました。
受講する科目の申請もして
授業料も振り込んでいました。
気持ちとしては
もうやめたい
と何度も思いましたが
その状態だからこそ
勉強することが
達成感につながりました。
嫌だと思うけど
必要なことを
今日も投げ出さずにやった。
という達成感。
テキストを開いて
読めずに終わる日もありました。
授業を視聴しても
なにも頭に入ってこない日もありました。
ですがそれでも
行動しただけ偉い
と思うことにしました。
うつや適応障害には
この小さな
行動しただけ偉い
が本当に重要です。
思考がネガティブに
いきやすくなっているので
ほめられる材料は
徹底的に使ったほうがいいです。
他人ならなんて言うか
とかは一切考えなくていいです。
自分にとっての達成感
であることが
まずは大事だと思います。
使う言葉の角をなくす
僕の場合
適応障害のきっかけは
パートナーとのケンカでしたが
さらに細かく見れば
ネガティブな思考の声
が原因でした。
この思考の声は
理性の防御反応ですが
そこで使われるボキャブラリーは
日頃自分が世間に向けて使っている言葉
と同じです。
自分の世界の見方が
そのまま自分への批判として
跳ね返ってきます。
なので
きつい言葉を使うことをやめました。
仕事に関することは
なんだそれ、認めねえぞ
みたいに思うこともありますが
そんなときも
責めるのをやめて
冷静に対象と原因を
分析するように心がけました。
若い時は
そう言う態度を
偽善的だ
と思っていたのですが
それ以前に
偽善的だ、と捉える自分の意識が
未成熟なだけでした。
実際言葉を変えると
見える世界が変わります。
冷静さも増しますし
周りの空気も変わります。
効果大です。
本当に。
先にあげた
行動しただけ偉い、も
意識して使った言葉のひとつです。
自分を苦しめているのが
自分の言葉をもとにした態度なら
言葉を変えればいいのです。
言葉は意図を超えて強力なので
使い方を機械的にでも変えるだけで
影響は出ます。
まずは言葉を変えて
自分に優しく接する
これが重要だと思います。
まとめ
良くなりたい
と思っただけでは奇跡は起きませんが
その思いを起点に
日常の中で小さな工夫を積み重ねることで
確実に自分の状態は変わっていきます。
朝の行動で一日のスタートを自分のものにして
自分なりの小さな達成感を積み上げて
ポジティブな言葉を使って自分を支える
これらは特別な道具も
コストも必要ありません。
それでも続けるうちに
自分自身の中に確かな
よくなっていく実感が
育まれています。
ここに書いたことが
考えるのきっかけになれば
幸いです。

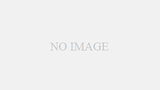
コメント